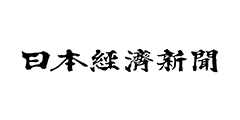- 知識ゼロから「まずは体験」とVRハードを導入
- VRは感情の部分でコミュニケーションが円滑になる
- 将来は誰かと行ける「バーチャルハワイ」が実現?
新規事業の担当者なら、AIやIoT、ロボット工学、5Gなどの先端技術と並んで、VRやARに興味を持つという方も多いはず。技術はそれだけでは価値を持たず、その道のプロが「この使い方ならうちの業界を大きく変えてくれそう」と活用方法を見出すことで、新しいビジネスに着地していきます。
今回は「コワーケーション」という新しい取り組みにSynamonの「NEUTRANS」を試験的に導入した株式会社J&J事業創造の會田悠太郎氏と西濱洋介氏にお話を聞きました。
知識ゼロから「まずは体験」とVRハードを導入
御社の事業について教えてください。
會田氏:我々はJTBとJCBが50対50で共同出資して2006年に設立した合弁会社で、社名の通り新規事業を生み出すのがミッションとなっております。もともとは両社の経営資源を生かして、例えば、「J&J Tax Freeシステム」というインバウンド向けのお店に免税システムを提供するような王道の事業をやっていたのですが、昨年度から新規事業開発により力を入れていくという方針転換がありました。
そこで技術も含めて広く調査して、次のビジネスの種を探しています。PoC(Proof of Concept、概念実証)としてトライしつつ芽が出始めている事業でいえば、インバウンドのお客様が海外に送付する「別送品」について、例えば伝統工芸品の少し大きいお土産を手持ちで持ち帰れない物を送る際、お店などで手続しなければいけない手間を簡素化するソリューションなどを手がけてきました。
そうした新規事業開発のために技術を調べていく中で、VRにも興味を持ったという?
會田氏:技術ありきで調査するというよりは、うちの既存事業に引っかかりそうなものを広く調べていました。VRももちろんその一部ではありますが、私が個人的に「VRChat」のような「ソーシャルVR」(VRゴーグルを使いインターネット越しにバーチャル空間に入って交流できるサービス)の世界に興味があったという理由もあります。
なんと!
會田氏:僕はVRハード自体を持っていなかったので、実はずっと試してみたいと思っていたところにSynamonとの出会いがあり、この機会に「まずは会社で導入しませんか」というところから始まりました。
新技術というと、企画を社内で通すのが大変ということも往々にしてありますが、大変だったのでは?
會田氏:いや、新規事業をつくるというミッションに切り替わっているので、リサーチの中の予算で比較的スムーズに導入できました。とはいえ僕らは、まだハードウェアすら持ってなかった段階なので、本当に初歩の初歩から始めた形です。
何に使えるのかがわからないから、まず自分たちで体験してみようという?
會田氏:そうですね。今後リサーチするにしてもハードは必要だから持とうという意図と、あとはちょうど2019年の4〜6月に京都府の舞鶴市でコワーケーションスペースを展開していたのでそこでも利用できないかと考えていました。
コワーケーション? コワーキングではなく?
會田氏:Co(共同)とWork(働く)、Vacation(休暇)を組み合わせた言葉がコワーケーション(Coworkation)です。バケーションとして普段と異なる環境に滞在しながら、その中で刺激を受けて仕事もやっていくという実証実験です。そのタイミングがSynamonとの出会いとがっちり合っていたので、例えばNEUTRANSを使って、舞鶴と虎ノ門オフィスをつないでみたら実際にどうなるのかというのを、自分たちで確かめてみたかったのです。
VRは感情の部分でコミュニケーションが円滑になる

開発本部マネージャー 會田悠太郎氏
最初にNEUTRANSを体験したときにどんな感想を持ちましたか?
會田氏:個人的に一番驚いたのが、ある程度事前にイメージしていたにも関わらず、バーチャル空間では声がその人がいる場所からきちんと聞こえてくるんです。あとは質感。恐らくSynamonの技術力が関わっている部分だと思いますが、同じボールでもピンポン球とサッカーボールで重さや反響音の違いなどが分かって、その辺のリアルさに驚きました。
初体験でもその辺の質感がわかるんですね。
會田氏:わかるぐらいにスゴかったというのが正直なところです。
個人的には、部屋の隅にあるコンセントまで忠実に再現しているようなこだわりがマニアックで好きです(笑)。
その観点は初耳です!
會田氏:「こんなところ絶対忠実に再現しなくてもわからないのに」って思いつつ、きちんと作り込んでいるのがさすがだなと思いました。
(笑)。先ほど舞鶴の話が出ていましたが、コワーケーションスペースではどういった使い方を?
會田氏:舞鶴の拠点では、モニターツアーでお招きした外部の方々にVRゴーグルを被ってNEUTRANSの空間に入ってもらい、私も東京からインターネット越しに同じ場所に入って案内しました。一番好評だったのは、空間ごと切り替えて360度映像を見せるという体験でしたね。かなりわかりやすくVRのすごさを直感できるので、最初の取っ掛かりとしてよかったという印象です。

赤レンガ倉庫内に作られた、舞鶴のコワーケーションスペースの様子。
NEUTRANS BIZは手前のテーブルに設置されている。
西濱氏:上の方を見上げながら「これすごい気持ちいいですね!」という声も聞きました。リアルに近くてどこかに行ったような気持ちよさを体感できるので、「これあったらもう旅行かなくていいよね」という反応をされた方も何人かいました。ここに食いつくんだなと。
會田氏:あとは、まったく初対面の方にも関わらず、仲良くなるまでの時間がリアルより短く感じたのも発見でした。「あっ、初めまして」といった最初にある緊張の時間を飛ばして、いきなりカジュアルにお話できるというのはVRで会うメリットだと思います。それは相手も感じていると思います。
VRを挟んだ方が意外と仲良くなれるという話はよく聞きます。ネット越しというと会話のタイムラグが気になるところですが……。
會田氏:タイムラグはまったく気にならず、自然でした。現状、まだVRはハードがソリューションに追いついていない部分が多くあると思う一方で、これはハードさえ付いて来れば一気にコミュニケーションのあり方が変わるなと。既存のビデオ会議よりも絶対に質の高い意思疎通ができますし、PCを画面共有しながらSkypeで……というよりも、感情の部分でコミュニケーションしやすくなる。
会議だったら資料をバーチャル空間にポッと浮かべておけますし、動画もテレビやプロジェクターを用意せずに空間の好きな場所に配置できるわけで、自由度が非常に高い。そこはひとつVRの魅力なのかなと思いました。
VRとNEUTRANSの両方の可能性を感じたという?
會田氏:感じましたね。NEUTRANSの本当に優れている点は、普通なら初めて何かの機械を使うときにもっと戸惑うところを、VRの操作に関して比較的初心者だった私でも感覚的に扱えたところです。
当時は舞鶴にずっと置いて使っていたのでしょうか?
會田氏:そうですね。回数は少ないですが、導入したからには実地でできる限りやっていきたいということもあり、弊社社員があちら側にいるときはミーティングの代わりに使っていたりもしました。
ネガティブ面としては、現状セットアップに慣れている人が少なかったりと、VRハードの課題が浮き彫りになった部分もあります。ですが確実に来るだろうと予見したときに、じゃあ私たちの会社が新規事業で何ができるのかというのは、今から先に考えておかなければいけない。そんな危機感は感じました。
将来は誰かと行ける「バーチャルハワイ」が実現?

取締役 開発本部 副本部長 西濱洋介氏
新規事業を考えたいというお話ですが、今、御社はVRでどんな未来像を思い描いていますか?
會田氏:JTBでも現在一部でVRでの遠隔旅行をやっていますが、それより誰かと一緒に旅行する体験のほうがわかりやすいと思います。例えば、体が不自由で1人で旅行に行けないご年配の方でも、忠実にモデリングされたバーチャルハワイを誰かと一緒に楽しめるとか。
確かに旅の楽しさを要素分解していくと、家族や友達と特別なところに行って、一緒に特別な体験するところにあります。
會田氏:だから、極論リアルじゃなくてもいいんじゃないかという視点はあると思います。ただ僕がソーシャルVRが大好きすぎて、そっちに意識がいきがちというのもありますが(笑)。
あとは先ほどのコワーケーションという話でいえば、VRが市民権を一定持ったあとに、「そもそもコワークって必要?」という話も出てきそうです。VR機器だけ持っていれば、ホテルの部屋でも仕事したいときに被れば仕事場になるわけですし。
飛行機のエコノミークラス席などの狭い空間でも、広い空間にいる感覚で仕事ができちゃう感じですよね。その遊びも仕事もNEUTRANSで実現できる世界だと思います。
會田氏:いつか一気にスケールすると思いますね。
西濱氏:僕らと違う観点でいえば、舞鶴市内の経営者を集めた方々の勉強会で体験してもらった際、たまたま看板屋の方がいて、「これからは看板もバーチャル化されていくから、そのうち自分たちは廃業していくんだろう」という声もありました。
リアルの看板がなくなって、広告のあり方だとかコミュニケーションの仕方は変わっていくのだろうと。そんな話をその場にいた市役所の方が聞いて、「現状、道路に看板を出す際には色々な規制があるけど、バーチャルとリアルで看板を出すようになった時代にはどう変わるんだろう」と話が発展していました。要するに都市生活の中にARやVRが入ってきたときに我々の生活はどうなるかという。
それは興味深い考察です。VRなどのXR技術が普及した際には、話しやすい空間でそのような議論が活発に交わされるのかもしれませんね。
西濱氏:そう思います。コワーケーションも同様ですが、VR空間のような場でみんなでワイワイガヤガヤと交流するのは、普段とは違う刺激をもらえて創造性がとても高まります。今後も両者のメリットを取り入れつつ、新規事業開発に取り組んでいきたいですね。