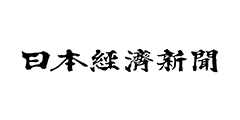- 「ちょっとアクセル踏みすぎ」じゃないと間に合わない
- VRだからできるスピーディーな意思決定
- VR空間からのロボット遠隔操作も視野に
ビジネスシーンにおいて、正確な情報を集められるかどうかは、既存の事業を伸ばしたり、新しい種を蒔くための意思決定で非常に重要な要素です。
そのために市場調査を行うわけですが、特にVRのような体験に価値がある先端技術を見極めるとなると、ネットや人づてで見聞きするだけは容易に理解できず、ゴーグルをかぶってコンテンツを試すのが必須となります。さらに言えば、自分たちでVRコンテンツまで作ってノウハウを蓄積し、「現状でもここまで使えるのか」「この用途にはまだ早いかな」と判断できるのがベストでしょう。
もちろん、まだ他社が手を出していない領域に投資するのはリスクがありますが、Synamonの「NEUTRANS」を利用すればゼロから開発するより時間やコストを抑えられるので、そのハードルをぐっと下げられます。今回はNEUTRANSを導入して、VRが何に使えるのかその可能性を探っていると語る、半導体試験装置の大手メーカー、株式会社アドバンテストにお話をうかがいました。
「ちょっとアクセル踏みすぎ」じゃないと間に合わない

フィールドサービス本部 副本部長 生貝重信氏
御社の主要業務について教えてください
生貝氏:弊社は1954年創業で、「計る」ということを中心に事業を創ってきました。創業当時は、マイクロアンメーターという微小電流を計測する製品を開発し販売しておりました。そのような測定技術から応用を経て、今は、ATEと呼ばれる半導体試験装置で、エレクトロニクス製品の品質保証とそれを通じた社会発展に貢献しています。
部門は大きく分けると「半導体・部品テストシステム事業」、「メカトロニクス関連事業」、「サービス他」の3つが存在します。前の2つは半導体に関わる試験装置の開発、販売、後の1つでは、主にテストシステムの設置やメンテナンス、新デバイスの量産テストの早期立ち上げ、テストフロア全体の稼働率向上といったお客様の生産性改善を提案しています。
拠点はヘッドクォーターである日本のほかに、北米、欧州、アジアほか世界各地に拠点構えており、従業員は約4,600人です。
それはかなり大規模ですね。国内の拠点も一ヵ所ではなく、全国に分散している感じでしょうか?
生貝氏:今となっては半導体の生産拠点の多くが海外に移転したため、弊社のお客様も9割以上が海外です。 日本国内は、東京、群馬、埼玉、名古屋、北九州などの拠点があります。現在、従業員の比率は国内と海外が半々くらいになっています。
国内外に拠点を多く抱えるからこそ、移動せずにVR空間で会って話せるNEUTRANSに興味を持った、という経緯でしょうか?
生貝氏:そうですね。拠点間でいかにコミュニケーションを取るかというのもひとつの要因ですが、元は自社で始めたリサーチがきっかけでVR自体に興味を持ちました。
弊社では年に2回技術発表会を開催し、様々なジャンルから有識者を呼んで世の中のトレンドを語ってもらうということをやっています。その中でヘッドマウントディスプレーの進化の歴史も含めてVRについて講演いただいたことがありました。
我々もちょうどその頃、フィールドサービス本部のFSイノベーションという部署を立ち上げた時期でVRに興味を持ち、以前、新企画開発に携わっていた神宮の人脈を使ってテクニカルリサーチをしたのがきっかけになっております。
神宮氏:NEUTRANSを知ったきっかけは、2018年12月に京都で行われたイベントでした。そのときは京都にいる自分と、東京の五反田にいるSynamonオフィスの技術者の方が同じバーチャル空間に入って、会話をしたりモノを手渡したりする体験をしました。まるで同じ空間にいるような不思議な感覚だった事を覚えています。
この衝撃的な体験を上司の生貝に報告し、即「VIVE Pro」を購入させてもらい、社内でもVRを体験できるような環境を整えました。

群馬R&Dセンタ フィールドサービス本部 FSイノベーション・神宮 裕二氏
体験してからのアクションが非常に早いことに驚きました
生貝氏:新しいことなので、具体的に何かきっかけをつくらないと動かない側面もあるのかなと考えてのことです。どの企業でも、世代交代や人口減少といった世の中の大きな流れの影響は避けられません。そんな状況下でも、社内の属人的な技術と新しいものを融合した要素を生み出していかないと、会社自体も立ち行かなくなっていくのではという危機感を抱いていました。施策としてはちょっと思い切ったものかもしれませんが、投資して挑戦しようというモチベーションでVRに取り組んでいます。
経験上、「こうしたいよね」と思ってから3年後ぐらいにリアルな波がやってくることが多かったため、「ちょっとアクセル踏みすぎでしょう」というぐらいじゃないと間に合わないのではという危機感が強かったのです。だから先行投資になってもやろうという思いで推進しています。
VRだからできるスピーディーな意思決定
拠点間でのコミュニケーションでは、どんな利用方法を想定していますか?
生貝氏:最終的には全ての拠点をつないでいきたいです。会議が非常に多いですし、やはりインタラクティブに話したいですよね。NEUTRANSのようなバーチャル空間に集まってコミュニケーションを取れるようになれば、移動の時間もお金も削減できる。今得た新しい情報に対処するために担当者を呼び出して、資料などを見ながら検討して次のアクションを決め、じゃあ進めていこうということをダイレクトにできるようにしたい。
単なるテレビ会議だとスピーディーな意思決定が難しいからVRを活用するという
生貝氏:はい。例えば紙の資料が3つあって、リアルの場なら並べて一度に情報を把握できるのに、テレビ会議だといちいち写真に撮って画面に映して、めくってという手間がかかるわけです。それがVRを活用して思い通りの感覚で対話を進められるなら、コミュニケーションの速度と質を上げられる。
実際、私の上司は、シンガポールに居て、様々なコミュニケーションツールを活用して毎日英語で会話しています。同様に社内で世界各地で国を超えたコミュニケーションが起こっているわけで、それがセキュアな状態でみんなで集まって資料を同時に見ながら話せるだけでも随分違うのかなと想います。
神宮氏:今導入しているオンラインミーティングサービスでも、ビデオ通話やテキスト、画面共有などが使えるので、それこそ社内のIT担当から「なぜVRが必要? 今のサービスでも補完できるのでは?」と言われがちなのですが、生のコミュニケーションと比べるとまだ思考を伝える速度が足りていない。
目の前で話している相手と同じことがシンガポールにいるエンジニアとできるかどうかという話です。そのできないというギャップをVRでどれくらい埋められるかという期待があり、じゃあテストしてみないとわからないよねというのが導入のモチベーションになりました。
ほかにもNEUTRANSには、保守業務で利用価値があるんじゃないかという話も出ています。
コミュニケーション以外の用途も視野に入れているのですね
酒井氏:例えば、機械内部のボード交換など、特殊な作業を含む修理方法をどうやって遠隔でサポートしていくのか。現状では、電話で話したり、メールで画像や文章を送って伝えていますが、やはり限界があります。もちろんお客様のところにエンジニアを派遣するのがベストですが、お金もかかる上、修理担当も時間を取られてしまう。
そこでVRやARの技術などを活用し、お客様が実際に作業しているところをバーチャルやリアルの空間に映し出して、同時に我々もその見ているものを把握した上で、関連資料を送るなり、「そこのボードを変えてください」と指示するなどできれば、トラブルシューティングの手助けになるのではと考えていました。

群馬R&Dセンタ フィールドサービス本部 FSイノベーション シニアディレクター・酒井裕二氏
世界で事業を展開している企業だからこそ、現地に行かなくてもバーチャル空間で同等の問題解決ができれば、人もお金も相当節約できそうです
酒井氏:社内のトレーニングへの活用も考えています。世界の各拠点には、それぞれテクニカルやサポートのエンジニアがいますが、日本のヘッドクォーターで開発した新しいテストシステムについてきちんと技術を伝授しないと、彼ら自身がお客様のところに行って直せないわけです。そのため現状は新機種が出たタイミングで、各拠点にテストシステムを持って行ったり、逆に日本に集まってもらって1、2週間教えるということをやっています。
技術を学ぶ上で重要なのは実物があることなのです。今の状態では時間もお金もかけていますが、VRやARの技術を使って、日本に来なくてもあたかもテストシステムそのものが目の前にあるような状態にしてトレーニングできればということを考えています。
VR空間からのロボット遠隔操作も視野に
実際にNEUTRANSを使ってみて魅力に感じた点は?
生貝氏:やはり先ほど説明した遠隔サポートやトレーニングですね。保守業務では、交換部品を相手先に発送して交換修理するだけでなく、その戻ってきた不良品を直すという作業もあります。つまり、オンサイトでやらなければいけないものと、時間はあるんだけど後で直せばいいという2つのパターンがある。これも世界中の拠点で行なっているため、コアエンジニアが現地のエンジニアを遠隔でアシスタントできるのではと思っています。
イメージは、VRで遠隔ロボットを操作する感じです。実際にそこまで必要かどうかは置いておいて、人がそこに存在してなくても操作できる可能性は今後あるんだろうなと。NEUTRANSは会議システムとして提供していただいていますが、その延長線上での可能性も視野に入れています。
十分に実現できると思います
神宮氏:遠隔手術のロボットもありますし、マイクロソフトのARゴーグル「HoloLens」も医療系に使われています。ほかにも人間がどうしても入れない場所に入っていけるというのも魅力だと思います。実際に稼働している機械の内部に頭を突っ込んで見ることは難しいことも多いですが、360度カメラを突っ込んで撮影して、その動画をNEUTRANSに配置してVRで体験できてしまう。
それはスゴいですね
神宮氏:NEUTRANSは、そうした様々なアイデアを手早く試せるのがいいところです。Unityなどを使って制作するとなるとコストも時間もかかってハードルが上がってしまいますが、NEUTRANSなら我々素人でも360度画像、映像を利用した臨場感のあるツアーコンテンツを簡単に作れてしまう。まずは「使ってみてなんぼ」で、そこから始まるのだと思います。
しかし、VRのような新しいことを試すにも人とお金を動かすわけで、それをこれだけの規模の会社で積極的に推進している姿勢は素晴らしいと感じました
生貝氏:私の海外に居るカウンターパートや弊社役員に「こういうものなんですよ」と実際にゴーグルをかぶってもらい紹介して進めています。そのかいあって
サービス部門を統括する役員からは、「多分ヘッドセットをつけて会議する将来がくるんじゃないか」という話が出ていました。その体験のために都度、会議室に機材をセッティングしなければいけない手間もあったりして結構大変なんですけどね。
神宮氏:早くメガネサイズになってほしいですよね。
VR業界でもその話はよく出ます。一方で、2016年には外部のセンサーを設置した上で、PCやゲーム機につないで使うというスタイルだったのが、わずか3年で「Oculus Quest」のような一体型が約5万円で買えるぐらいの速度で進化しているので、さらに3年先も大きく状況が変わっていると思います。最後にそうしたVRの少し先の未来について想像していることをお聞かせください
生貝氏:VR技術について期待しているのは、先ほど触れた遠隔操作ですね。HMDに加えて、入力と触覚のフィードバックを得られる装置も出てきて、それを実際のビジネスに役立てていけるレベルになってほしいです。例えば、ある場所に置いた装置を日本、ドイツ、アメリカ……とタイムゾーンが異なる地域から遠隔操作し、24時間フル活用して仕事を進められる、といった使い方です。
あとはVRと9軸ロボットのようなオートメーション技術が融合して、アプリケーションの幅が広がるというのも想像している未来です。半導体の製造業界でも自動化がひとつのテーマになっていて、我々のお客様の中にもテストフロアは無人で、電気を消した中、ロボットがトレーを運んでいるというところもあります。そうした最先端の状況に合わせたサービスやサポートを、弊社の内部的にも展開していきたいです。